仮想通貨の確定申告とは?基礎知識を初心者でもわかりやすく徹底解説
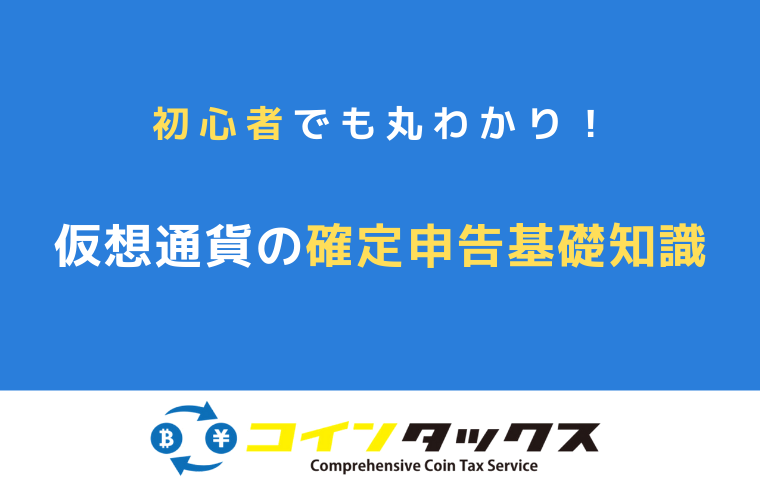
仮想通貨の取引で利益を上げたら納税をしなければなりませんが、納税のためには、納税額を確定するための「確定申告」をしなければなりません。
会社員の方の場合、確定申告は会社が代わりにやってくれているので、確定申告自体をやったことがない人がほとんどだと思います。
仮想通貨で利益を出したのに、確定申告をしなかった場合、脱税となり、罰金が課されてしまう可能性もあります。
そんなことにならないように、確定申告の仕組みを正しく理解し、きちんと申告をする必要があります。
確定申告自体は、それほど難しいものではありませんが、全くの初心者の場合は少し厄介に感じるものです。
そこで、この記事では、確定申告の基礎知識について、わかりやすく解説したいと思います。
仮想通貨で確定申告が必要となるケース

そもそも確定申告とは、その年1月1日〜12月31日の期間内の所得を計算し、確定申告書を税務署へ提出して、所得税額を確定することを言います。
計算を終えて、必要な書類をそろえたら、税務署に持ち込み、提出してから納税という形になります。ちなみに、確定申告の時期は、毎年2月16日〜3月15日となっています。
仮想通貨の確定申告はというと、仮想通貨の取引で得た所得を計算して、所得税額を確定する場合に、確定申告が必要となります。
仮想通貨の確定申告が必要となる利益額
基本的には、仮想通貨で利益を得た場合には確定申告をして納税をしなければなりません。
どれくらいの利益が出たら確定申告をしなければならないかは、納税する対象者によって違いますので、注意が必要です。
対象者別の、納税が必要となる所得金額は以下の通りです。
- 会社員:仮想通貨取引で20万円以上の所得が出た場合
- 専業主婦、学生(被扶養者):仮想通貨取引で38万円以上の所得が出た場合
- 個人事業主:所得の金額に関係なく確定申告を実施する
これらの条件に該当する場合には、確定申告を実施しましょう。
利益があるのに確定申告をしないと罰則を受ける
確定申告をしないといけない条件に該当するにも関わらず、確定申告をしなかった場合、脱税となる可能性があります。
脱税になった場合には、附帯税と呼ばれる、いわゆる罰金が課され、さらにたくさんの税金を払わなければならなくなります。
匿名性が高い仮想通貨であれば、バレないのではないかと思うかもしれませんが、最近では法整備が進み、国税庁は、取引所にユーザーの照会をすることもできるようになっています。
税金を納めないとほぼ間違いなくバレますので、きちんと確定申告をしましょう。
(補足)会社員で、利益が20万円未満だったら納税しなくていい?
ちなみに、会社員の場合で、利益が20万円未満であれば納税しなくても良いか、と言われると、それは違います。
確定申告は税務署の管轄する国税を納めるためのものですが、国民は地方税も納めなければなりません。地方税については、所得20万円未満の控除というのはありませんので、確定申告はしなくても住民税は納めないといけません。
詳しくは、こちらの仮想通貨の税金はいくらから納めないといけないのかに関する記事を参照ください。
仮想通貨の確定申告額の計算について

仮想通貨の確定申告額は、1年間の仮想通貨の取引による利益がいくらかを計算し、それに税率をかけることで算出することができます。
仮想通貨の取引と一言で言っても、様々なケースがあります。ここでは、主な取引の例をあげることにします。
- 仮想通貨を売却した
- 仮想通貨で商品を購入した
- 仮想通貨同士の交換を行った
- 仮想通貨の分裂(分岐、ハードフォーク)によって仮想通貨を取得した
- 仮想通貨を採掘(マイニング)により取得した
- 仮想通貨をエアドロップで受け取った
- ICOで仮想通貨を購入した
- 仮想通貨を贈与や相続で取得した
このうち、どれについて利益を計算しないといけないかというと、「基本的に全ての取引」ということになります。
年に数回しか取引をしない場合には、都度都度、取得価額と売却価額の差額を計算すれば良いのですが、年に数十回、数百回など取引の頻度が高い場合には、取得価額の平均を取って計算をすることもできるようになっています。
仮想通貨の税金に関して、もっとも複雑で面倒なのがこの所得の計算方法となります。この記事で詳しく書くと非常に長くなってしまいますので、詳しい利益の計算方法については、こちらの記事にて解説をしています。ぜひご参照ください。
確定申告時の提出書類

確定申告時の提出書類は、以下のようなものがあります。
- 確定申告書(確定申告書AまたはB):事業所得などがある方はBになります。
- 添付書類(源泉徴収票など)
- 控除を受けるための証明書類:医療費、生命保険、住宅ローンなど所得控除を受けるための証明書
-
マイナンバー確認書類、その他本人確認書類
詳しくは、以下の国税庁公式Webページを参照ください。
参考:国税庁|【申告書の提出】
確定申告書類の作成について
確定申告書類は、税務署などにいけば紙のものをもらえますが、国税庁のWebページ上で作成することも可能です。詳しくは、以下のリンクを参考にしてみてください。
参考:国税庁|よくある質問コーナー(仮想通貨の取引に係る収入がある場合)
確定申告のために準備する書類
確定申告をするために、仮想通貨の取引に関する書類が必要です。
- 仮想通貨取引履歴に関する書類
- 仮想通貨の入金・出金明細書
- 各ウォレットの残高のスクリーンショット
- 年間損益報告書
これら、取引の明細については、提出は不要です。
しかし申告後に、税務署から問い合わせが来ることもありますので、資料は確実に入手し、保管しておきましょう。
申告してから5年間は、問い合わせの可能性があります。
確定申告の時期について

仮想通貨取引による利益を確定したら、確定申告資料を準備し、確定申告をします。
確定申告の時期は、毎年2月16日〜3月15日で、前年の1月〜12月の取引履歴について申告をすることになっています。
2019年の利益について申告をする場合には、確定申告時期は2020年の2月16日〜3月15日です。
なお確定申告は、全国の税務署で実施します。地域によっては確定申告時期に特別会場が開設されることもありますので、詳しくは国税庁のWebページで確認してみてください。
確定申告は、わかってしまえばそれほど難しくない
この記事では、確定申告に関する基礎知識をまとめましたが、それほど難しい内容ではなかったかと思います。
仮想通貨の税金に関して一番面倒なのは所得の計算に関する部分で、個人個人で状況が違うため、悩む場合があるかもしれません。
詳しくは、仮想通貨の税金の計算方法に関する記事を参照してください。
また、計算方法について解説を見てみたけど、よくわからないという場合には、税理士に相談してみるのも手だと思います。
計算方法はもちろんのこと、節税方法なども状況に合わせて提案できますので、まずは問い合わせから気軽に相談ください。