初心者でもわかる仮想通貨の税金の基礎を徹底解説
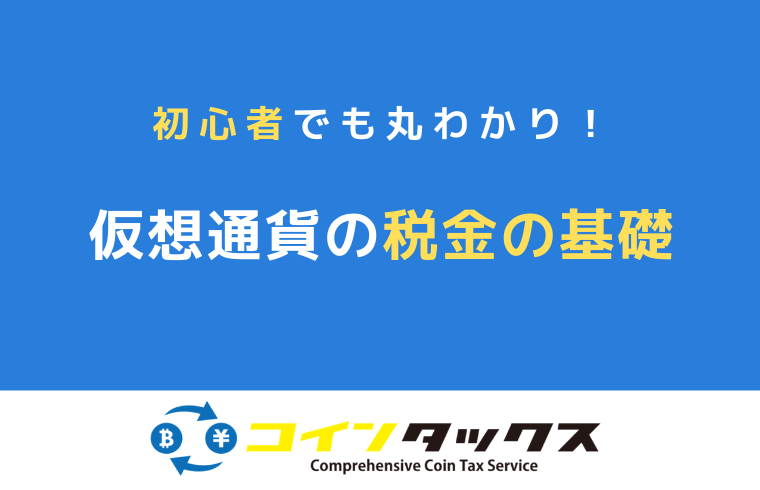
仮想通貨の取引によって利益を得た場合、その利益は原則的に課税の対象となります。
仮想通貨は匿名性が高く、確定申告しなくてもバレないのではないかと考える方もいるかもしれませんが、税務署が銀行や取引所に対して税務調査を実施できるようになってきているので、間違いなくバレてしまいます。
そして脱税がバレると、本来払うべき税額よりも余分に納税しないといけなくなる可能性もありますので、きちんと確定申告をして、きちんと納税をする方が、結果的にはお得になるということですね。
とはいえ、仮想通貨の税金についてきちんと理解し、正確な金額を納税するというのは、難易度が高いと感じる人が多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、仮想通貨における税金の取り扱いなどの予備知識と、納税の仕方についてわかりやすく解説します。
仮想通貨の税務上の取り扱い

国税庁が発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(平成31年2月)」によれば、仮想通貨の取引によって得た利益は、「雑所得」に区分されます。
所得税は、その内容ごとに10種類に分類されます。簡単に説明すると、以下のような区分となっています。
| 番号 | 所得の種類 | 説明 |
| 1 | 利子所得 |
預貯金や公社債の利子、および合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配などに係る所得 |
| 2 | 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当、投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 |
| 3 | 不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権、船舶や航空機の貸付けによる所得 |
| 4 | 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
| 5 | 給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
| 6 | 退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
| 7 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得 |
| 9 | 一時所得 | 上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの |
| 10 | 雑所得 | 上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得。仮想通貨の取引によって得られた所得は「雑所得」に区分される |
仮想通貨取引によって得られた所得は基本的には雑所得と考えて良いのですが、仮想通貨取引の収入によって生計を立てている場合や、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として使用した場合には、雑所得ではなく「事業所得」として取り扱います。
事業所得として認められた場合、「損益通算」ができるかという点で、雑所得よりも納税の上で有利になる場合があります。
より詳細には、国税庁Webページを参照ください。
仮想通貨が区分される雑所得は「総合課税」の対象となる

仮想通貨取引による所得は「雑所得」に区分されますが、雑所得は「総合課税」の対象となります。
総合課税とは、総合課税の対象となる区分の所得を合計して、所得税額を計算するものです。
総合課税とは別に分離課税という制度もあり、為替FXなどの先物取引で得られた所得は分離課税に区分されます。
では仮想通貨のFX(先物取引)はどうなるのか?と疑問に思われるかと思いますが、仮想通貨は金融商品取引法の対象とはなっていないため、仮想通貨に関しては、先物取引であっても総合課税となります。
総合課税の区分には、以下のようなものがあり、仮想通貨以外の所得がある場合は、合算した所得に対して税率がかかることになります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
ただし、株式などの譲渡による所得、源泉分離課税とされる所得など、総合課税には含まないものもあります。また、4、6、8に係る所得の計算においては、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
仮想通貨の取引は一般的に、全て総合課税制度の対象となりますが、その他の所得と合算して計算する必要があるため、株式や金融先物商品などの取引がある場合には、注意が必要です。
詳しくは、以下の国税庁の資料をご覧ください。
参考:国税庁|総合課税制度
仮想通貨所得の税率

仮想通貨取引で得た所得は総合課税であり、その他の所得と合算した金額を元に、収めるべき税額を計算することになります。
つまり、給与所得、事業所得(副業をしている場合)、利子所得や配当所得(有価証券など所有している場合)など仮想通貨取引による雑所得がプラスされて、所得額が計算されるということです。
こうして計算された所得の総金額に対して、所得税率がかかり、納税額が決定されます。
所得税は先ほども書きましたが、所得の金額に応じて課税率が大きくなる「累進課税」方式となっており、個人にかかる所得税率は、下記のようになっています。
- 195万円以下 所得税率5%
- 195万円〜330万円 所得税率10%
- 330万円〜695万円 所得税率20%
- 695万円〜900万円 所得税率23%
- 900万円〜1800万円 所得税率33%
- 1801万円〜4000万円 所得税率40%
- 4000万円〜 所得税率45%
利益が大きなればなるほど、所得税の税率は上がり、収入が4000万円を超えると所得税率は最大45%にもなります。
さらに、ここに住民税が一律10%加算されますので、「仮想通貨の利益のうち、最大で55%は税金として取られる」ということになります(実際の計算は、もう少し複雑となります)。
参考:国税庁|所得税の税率
仮想通貨の所得は、いくら以上だったら納税が必要になる?

仮想通貨の所得は、いくら以上になったら納税が必要になるかについては、納税の対象者や、納税先によって異なります。
対象者別に、納税の必要が生じる所得の金額をまとめると、以下のようになります。
| 対象者 | 所得税を納める必要がある所得の金額 | 住民税を納める必要がある所得の金額 |
| 会社員 | 20万円 | 所得の金額に関係なく納税する |
| 主婦・学生(被雇用者) | 38万円 | 33万円(自治体によっては35万円) |
| 個人事業主 | 所得の金額に関係なく納税する | 所得の金額に関係なく納税する |
なお、仮想通貨の税金は、利益がいくらからかかるのかについての記事も書いていますので、参考にされてください。
仮想通貨の所得の計算方法

利益を計算する必要がある仮想通貨取引の種類について、国税庁が発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(平成31年2月)」を元にして解説します。
仮想通貨の取引と一言で言っても、様々なケースがあります。ここでは、主な取引の例をあげることにします。
- 仮想通貨を売却した
- 仮想通貨で商品を購入した
- 仮想通貨同士の交換を行った
- 仮想通貨の分裂(分岐、ハードフォーク)によって仮想通貨を取得した
- 仮想通貨を採掘(マイニング)により取得した
- 仮想通貨をエアドロップで受け取った
- ICOで仮想通貨を購入した
- 仮想通貨を贈与や相続で取得した
このうち、どれについて利益を計算しないといけないかというと、「基本的に全ての取引」ということになります。
年に数回しか取引をしない場合には、都度都度、取得価額と売却価額の差額を計算すれば良いのですが、年に数十回、数百回など取引の頻度が高い場合には、取得価額の平均を取って計算をすることもできるようになっています。
仮想通貨の税金に関して、もっとも複雑で面倒なのがこの所得の計算方法となります。この記事で詳しく書くと非常に長くなってしまいますので、詳しい利益の計算方法については、こちらの記事にて解説をしています。ぜひご参照ください。
仮想通貨の利益にかかる税金を納税する方法

仮想通貨の利益にかかる税金を納税する時の、基本的な流れは以下のようになっています。
- 各取引所から1年分の取引履歴をダウンロードする
- 仮想通貨取引の利益を計算する
- 計算結果を確定申告資料に記載して提出、納税をする
実際のところ、確定申告資料を作ること自体は、そんなに大変ではありませんが、利益の計算がもっとも大変な箇所です。
計算を終えて、必要な書類をそろえたら、税務署に持ち込み、提出してから納税という形になります。
確定申告の時期は、毎年2月16日〜3月15日となっています。この期間中に、税務署に必要書類を持ち込む必要があるのですが、3月になると混み合います。
確定申告は、年度ではなく年単位での計算を実施します。例えば2019年の確定申告をする場合、2019年1月〜12月の取引履歴をダウンロードし、所得を計算します。
ですので、年が明けたら前年の利益の計算を開始し、2月中に確定申告を済ませてしまう方がおすすめです。
仮想通貨の税金は納めないとバレる?
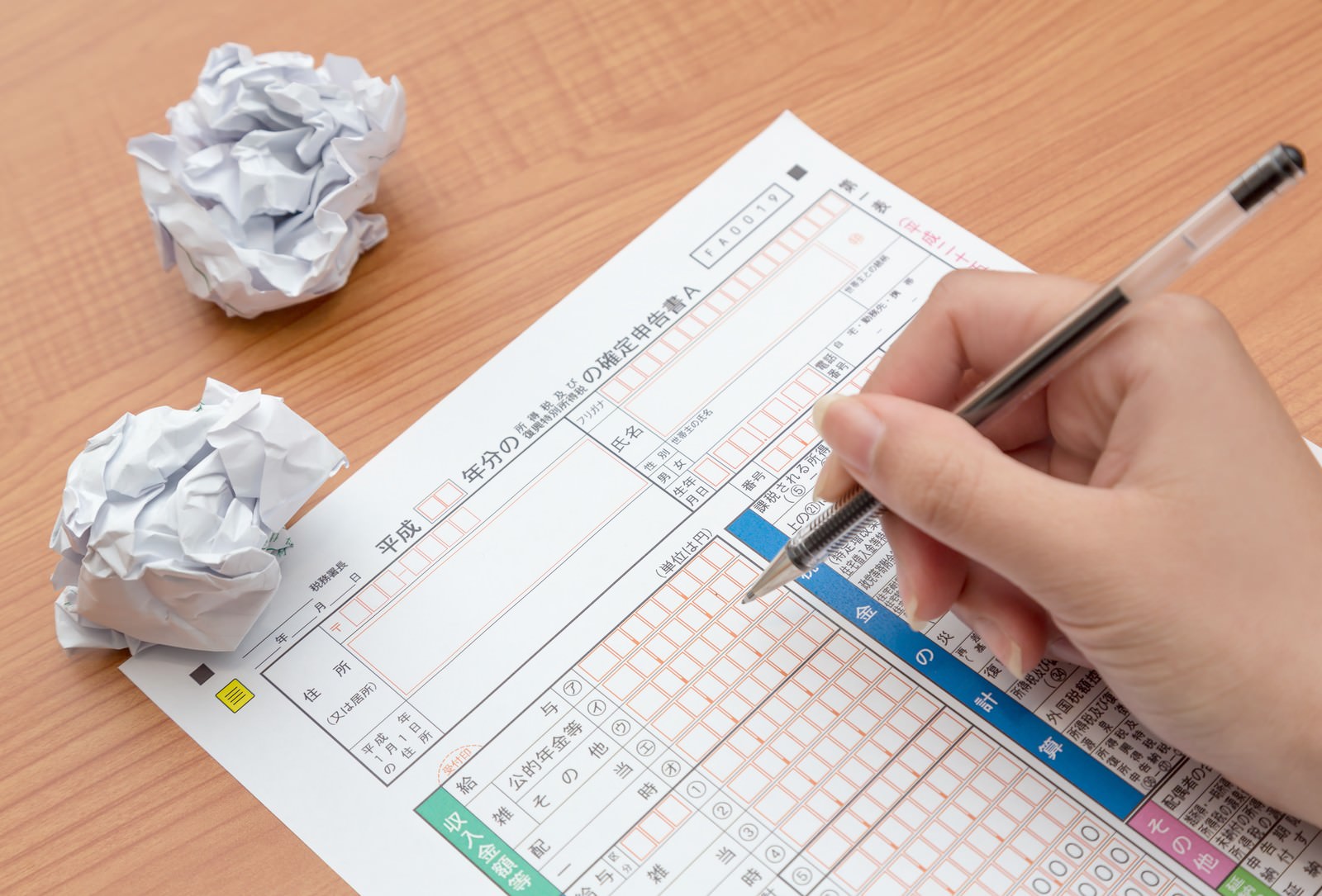
さて、ここまで仮想通貨の税率がどれくらいになるのかや、納税の方法などを説明してきました。
仮想通貨の所得にかかる税金は、とても高額になるというのがわかったので、できれば税金を納めたくないと思うのが人情ですよね。
「仮想通貨の税金は高すぎる・・・いや待てよ。仮想通貨は匿名性が高いから、納税しなくてもバレないのでは?」
と考える方もいるかもしれません。
残念ですが、結論をいうと、「仮想通貨の税金は納めないとバレます」。
税務署は、取引所に対してユーザー情報の開示を求めることができる
仮想通貨やシェアリングエコノミーなど、「広域的、国際的な取引が容易で、取引の実態がわかりにくいサービス」に関する国税庁の調査は、年々強化がされています。
仮想通貨の項目に関して言えば、「現⾏実務上⾏っている事業者等に対する任意の照会について、税法上、国税当局が事業者等に対して協⼒を求めることができる旨が明確化」されたとあります。
つまり、怪しいユーザーは、税務署が取引所に照会をかけて、情報を開示させることができるということです。
実際に、国税庁から取引所に照会をかけ、脱税が発覚したケースがあるとの報告もされています。
参考:シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応
仮想通貨取引で100億円分の申告漏れが指摘されている
取引所への照会を実際に行なった結果、2019年6月には、100億円の申告漏れが指摘されたという新聞報道がありました。しかも、過去数年に遡っての調査となっています。
これほどの額が示すように、バレないと思っている人はこんなに多いということもわかりますが、バレてこれから大変な目に合う予定の人も多いと言えてしまいますね・・・。
脱税がバレるとどうなる?
脱税がバレると、「付帯税」というペナルティーが課されます。
要は、本来支払うべき税額に対して、追加で罰金を支払わなければならなくなるというイメージです。
また、仮想通貨の根幹となっているブロックチェーンは改ざんできない取引記録となっているため、一度ウォレットアドレスが発覚すれば、過去まで遡って税金を徴収されることにもなります。
期限までに支払われなかった場合には付帯税のうち、延滞税などもかかってくるため、期限(その年の所得税はその年に収める)もしっかりと守らなければなりません。
脱税ではなく節税を
脱税はバレますし、バレたらペナルティもあります。しかも、もし税金が払えなくなったとしても、税金を理由とした自己破産もできません。
まずはしっかりと税金を納めないといけないということを認識してほしいと思います。
それでも、どうしても税金を払いたくない場合は、脱税ではなく節税を考えてみてください。
節税は、税制度を上手に使った税金対策で、仕組みを理解し、活用することでかなり税金を抑えることができます。
詳しく知りたい方は、税金対策・節税方法を6つ紹介したこちらの記事を参照ください。
仮想通貨の納税は早めに検討を開始しましょう
というわけで、仮想通貨の税金の予備知識、納税方法について解説しました。簡単にまとめると、以下のようになります。
- 仮想通貨の所得税は雑所得に区分され、総合課税制度が適用される
- 仮想通貨の取引においては、取引回数が多い場合、利益の計算方法がとても複雑になる
- 仮想通貨の納税は確定申告で実施する
- 仮想通貨の税金は納税しないとバレる。脱税ではなく節税を。
仮想通貨の税制については、国税庁の公式文書もあまりなく、事例も少ないため、「国税庁の資料を読んでみたけど、理解できない」ということも十分にありえます。
自分のケースに当てはめた時、どうなるのかよくわからないという場合には、税理士に相談することも視野にいれてはどうでしょうか。
まずはお気軽に、問い合わせから相談してみてください。